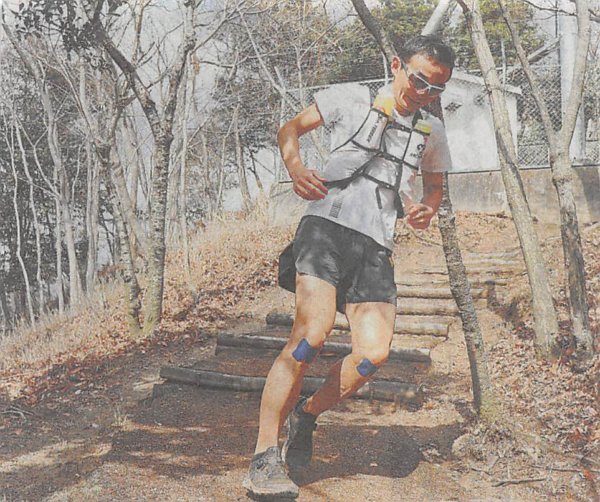Akimasa Net
ひろしま百山(私の踏み跡)>> 広島湾岸トレイル >> 武田山/大茶臼山トップページ
広島湾岸トレイル(モデル山行記)
武田山~火山~丸山~大茶臼山
(出発:JR大町駅―可部線、帰着:己斐峠(JR西広島駅―山陽本線))
2016年01月16日(土)、広島湾岸トレイル体験登山(第13回)

〈写真〉火山から雪をかぶった深入山を見る、12時31分
(画面左の最奥に、西中国山地の深入山を見る)
- 今日の山行ルート図 ⇒ GPS軌跡(2016年01月16日)モデルコース
- 道標写真多数有り ⇒ Akimasa Net(2016年12月17日)山行記
- 小4と一緒に歩く ⇒ Akimasa Net(2017年01月07日)山行記
このページの目次です
はじめに
太田川右岸の縦走路である。その周囲は360度団地で囲まれている。古くから住んでいる人や新しい人、様々な個人や団体が、それぞれの思いで山の手入れをされている。
今日はそうした人たちに、大町観音水、大町古墳、ガガラ山、吹き通し、火山そして権現峠でお話を伺う。感謝! 今日一日中マイクを持っての先導があり、これまた感謝!
今日のコース&コースタイムは、各箇所での案内に時間を要したことや一部コース変更があり、参考まで。(大町観音水と大町古墳はコース外)
今日のコース&コースタイム
JR大町駅(10m未満)8:37-大町登山口(20m前後)8:51、8:54-名水分岐(120m台)9:06-大町観音水(110m前後)9:11、9:14-大町古墳(160m台)9:22、9:29-大町コース合流9:29-200m台9:34-武田山分岐(200m台)9:37-カガラ山(212m)9:40、09:51-武田山分岐(200m台)9:56-吹き通し(160m台)10:00-憩いの森分岐10:04(200m台)-展望広場(320m台)10:20、10:26-空堀跡(380m前後)10:37-見張り台(390m台)10:41-武田山(410.5m)10:49、10:57-弓場(390m台)11:03、11:08-鞍部(270m台)11:21-353m11:31-(水越峠、320m台)11:35-350m台11:43-火山(488.0m)12:02、12:33-展望(430m台)12:40、12:45-伴峠12:53-小堀山(399m)13:00-権現峠(350m台)13:05、13:23-石山(420m台)13:34、13:36-送電線鉄塔(426m)13:42-大塚峠(380m台)13:51-湯つぼ跡13:52、13:54-丸山(457.4m)14:03、14:10-送電線鉄塔(356m北側)14:30、14:35-畑峠(320~330m前後)14:41、14:43-大茶臼山(413.0m)14:59-ガードレール越え15:02-展望岩(立石城跡、390m前後)15:06、15:10-己斐峠(190m台)15:36
- JR大町駅(14分)大町登山口(28分)大町古墳(11分)カガラ山(9分)吹き通し(20分)展望広場(23分)武田山
小計1時間45分(大町観音水3分を含む、大町登山口3分、大町古墳7分、がガラ山11分、展望広場6分を加えず) - 武田山(34分)353m(31分)火山
小計1時間05分 - 火山(27分)399m(5分)権現峠(19分)426m(21分)丸山
小計1時間12分(権現峠18分を加えず) - 丸山(20分)送電線鉄塔(356m北側)(6分)畑峠(16分)大茶臼山
小計49分(送電線鉄塔5分、畑峠車道2分を加える) - 大茶臼山(7分)展望岩(26分)己斐峠
小計37分(展望岩4分を加える)
- 総合計(全ての時間を含む)
6時間59分
火山から深入山や恐羅漢山は見えるか
火山山頂で「深入山が見える」と声があがる。指差す方向に雪をかぶったきれいな円錐形が浮かんでいる。「距離30km」との声が続く。よく調べていらっしゃる方のようである。
私がカシミールで改めて検討した結果では、深入山(標高1152.5m、直線距離30.0km、方位316.2度(真北から))となった。

〈写真〉雪をかぶった深入山を見る、12時31分
(画面左の最奥に、西中国山地の深入山を見る)
この前の体験登山で聞いた話では、西中国山地に今年はほとんど雪がなくて、かろうじて輪カンの練習ができたということだった。その後の冷え込みで少し雪が降ったのだろう。
さて、西中国山地にもう一箇所、東郷山の右奥に雪で白くなった山並みが見える。私は「恐羅漢山」とみた。ところが、2日に一度火山に登っているという地元の方の話では、ここから恐羅漢は見えない、とのこと。
恐羅漢山についても改めて検討してみた。恐羅漢山は、見通しさえ良ければ火山からはっきりと見ることができるはずである(東郷山との角度差17.6度)。参考までに以下まとめてみた。
向山の左肩に、窓ヶ山(710.7m、9km、259.8度)の双耳峰をみる。窓ヶ山のさらに左奥に、大峰山(1039.5m、20.4km、257.9度)の三角錐が美しい。
大峰山から連なる阿弥陀山が、窓ヶ山~向山の右肩に頭を出す。阿弥陀山からさらに右に、東郷山(977.1m、11.8km、281.8度)に向けて尾根が連なる。
窓ヶ山と東郷山の角度差は、約22度である。東郷山からさらに右に、標高800m台の尾根が293度くらいまで続いている(東郷山との角度差は約11度である)。
今日雪山を見たのは、それらの右奥である。
十方山(1318.8m、29.2km、294.1度)又は恐羅漢山(1346.2m、32km、299.4度)である。さらに詳しく検討すると、十方山~恐羅漢山の間に、前三ツ倉や丸子頭が見えるという。
十方山は、東郷山の尾根の右奥にかろうじて頭をのぞかせる程度と考えられるので、今日はっきりと姿を現していたのは恐羅漢山で間違いないだろう。写真にうまく撮れなくて残念である。
注1) 方位は真北からの数値。ところで、広島地方では磁北は約7度くらい西偏している。つまり、真北からの数値に7を加えると、磁北からの方位(角度)になる。
注2) 方位角が約10度の差とは、人差し指と中高指でピースサインを作って、腕を前方に突き出したときの角度。
注3) 方位角が約2度の差とは、人差し指だけを突き出したときの指の幅。
JR大町駅~登山口
武田山は、JR(可部線)やアストラムラインの最寄り駅から歩くことのできる山である。今日はJR大町駅から概ね西向きに登山口を目指す。(GPS軌跡参照)

〈写真〉JR大町駅近くから武田山を望む、8時39分

〈写真〉町並みをぬって登山口を目指す、8時44分
(前方に武田山を見る)
大町登山口(標高90m前後)である。

〈写真〉大町登山口、8時49分
(車道の右手から取り付く)
登山口~大町観音水~大町古墳~ガガラ山
気持ちの良い疎林を行く。所々にツバキの花が落ちている。ここは照葉樹林帯である。そしてここから距離30km先には、西中国山地(落葉広葉樹林帯)を見ることができる。東アジアを二分する樹林帯を2つとも体感できる非常にぜいたくな空間である。

〈写真〉気持ちの良い疎林、8時59分
今日は、広島湾岸トレイル(HWT)の正規ルートを外れて、大町観音水を見学することになっているようである。標高120m台で正規ルートの尾根筋を外れ、左手巻道をゆったりと行く。

〈写真〉大町観音水分岐、9時06分
大町観音水(標高110m前後)を見学する。

〈写真〉大町観音水、9時13分
大町観音水からほんの少し西向きに行き、南に流れる尾根を北向きに登る。大町古墳(標高160m台)まで登ると、武田山北東面~鞍部(吹き通し)が大きく姿を見せており美しい。

〈写真〉大町古墳から武田山を見る、9時26分
大町古墳を見る。

〈写真〉大町古墳、9時29分
大町古墳から、さらに北向きに尾根を行く。
ガガラ山山頂から、武田山~火山を見る。ガガラ山の山頂部では、近年度重なる山火事があり、その後片付けをした結果、現在の展望が得られるようになったという。今では、武田山登山のメインルートになっているようである。皮肉なことである。
ガガラ山から武田山、火山を見る。北側から見ると、武田山が三角形、火山がなだらかに見える。なおGPS軌跡では、ガガラ山の位置は地理院地図の212mではなく、その一つ南側の210m台となっている。

〈写真〉ガガラ山から武田山、その右奥に火山を見る、9時48分
ガガラ山~武田山
武田山分岐(標高200m台)まで引き返して右折、吹き通し(鞍部、標高160m台)まで下る。地理院地図黒実線のとおり南西向きに下る。
吹き通しは、その昔は北と南を結ぶ交通路だったようである。

〈写真〉武田山分岐から見る武田山、9時56分
吹き通し(鞍部、標高160m台)手前である。

〈写真〉吹き通し、9時59分
吹き通しからも南西向きに行く。ほぼ尾根筋を登るものの、武田山山頂まで地理院地図に表示はない。

〈写真〉10時04分
展望広場(標高320m台)を過ぎ、空堀跡(標高380m前後)、見張り台(標高390m台)そして館跡から武田山山頂(標高410.5m)に達する。

〈写真〉空堀跡、10時37分

〈写真〉見張り台、10時41分
武田山山頂(標高410.5m)に達する。

〈写真〉武田山三角点、10時49分
武田山~火山~権現峠
武田山から火山~丸山~畑峠まで、尾根筋に国土地理院黒破線が表示されており、ほぼほぼそれに従って進む。
山頂部の弓場には、遊具(弓と矢、そして的)が備え付けられている。

〈写真〉弓場で遊ぶ、11時04分
武田山から一旦大きく下り、登り返して火山山頂(488.0m)に達する。

〈写真〉火山三角点、11時04分
縦走路の右も左も大団地に囲まれている。火山の先の展望箇所(標高430m台)から、左手(尾根南東面)に開かれた大団地を見下ろす。

〈写真〉火山南側の大団地、12時43分
(画面右手、送電線鉄塔426m(右)と丸山(左)の間に大茶臼山が頭を出す。それらの左手奥には宗箇山)
権現峠(標高350m台)をほんの少し西向きに下った所に権現神社がある。

〈写真〉権現神社の真新しい案内板、13時06分
権現峠~丸山~大茶臼山
権現峠から丸山~大茶臼山までは、あまりアップダウンはないので、思った以上に距離を稼ぐことができる。
権現峠のすぐ先(標高420m台)から、今度は尾根右手前方に造成中の団地を見る。

〈写真〉右前方で宅地造成中、13時34分
丸山三角点(457.4m)に達する。

〈写真〉丸山三角点、14時03分
畑峠(標高320m前後)で舗装道路に出る。

〈写真〉畑峠、14時41分
舗装道路に出て左折、東向きにほんの少し舗装道路を歩く。右手に折り返す(標高330m前後)ようにして再び山道に入る。

〈写真〉大茶臼山取り付き、14時43分
(畑峠から大茶臼山に取り付く)
畑峠(標高330m前後)から大茶臼山(413.0m)まで、尾根筋の境界表示に従って疎林の中を登る。山頂部施設の脇を通り抜けてゆく。

〈写真〉山頂部の施設横を行く、14時54分
大茶臼山三角点(413.0m)に達する。

〈写真〉大茶臼山三角点、14時59分
大茶臼山~己斐峠
大茶臼山三角点(413.0m)から南向きに少し行く(地理院地図黒実線)。ガードレールの隙間から車道へ出る。左手施設の横を通り過ぎ、施設角で左折してなおも南向きに下ると展望岩場(標高390m前後)がある。

〈写真〉大茶臼山三角点から南に行く、15時00分

〈写真〉ガードレール切れ目から車道へ、15時02分

〈写真〉施設角を左折する、15時03分

〈写真〉展望岩場、15時06分
展望岩場から岩場をすり抜けて下り、南向きに地理院地図の境界表示に従って下れば己斐峠である。

〈写真〉岩場をすり抜けて下る、15時11分

〈写真〉己斐峠、15時35分
己斐峠からボン・バスでJR西広島駅まで帰り着く。
国泰寺(広島市)
安国寺恵瓊(毛利氏に仕えた外交僧)が現在の広島市中区中町に創建。1978年(昭和53)己斐に移転して現在に至る。大石内蔵助(忠臣蔵)の妻りくの墓がある。内蔵助の遺児大三郎は、赤穂浪士吉良邸討ち入り後、浅野本家(広島藩)に1,500石で召し出され、母りくも広島に同行し同地で没した。
見える山のリスト(火山)
以下、360度の展望が開けると仮定した場合、見える可能性の高い山のリスト。
注1)方位は真北からの数値。ところで、広島地方では磁北は約7度くらい西偏している。つまり、真北からの数値に7を加えると、磁北からの方位(角度)になる。
注2)方位角が約10度の差とは、人差し指と中高指でピースサインを作って、腕を前方に突き出したときの角度。
注3)方位角が約2度の差とは、人差し指だけを突き出したときの指の幅。
番号、山名、標高、直線距離、方位(真北から)
1、火山、487.9m、0km、0度
2、後山権現山、490m、6.7km、8.4度
3、水越山、525.7m、8.6km、13.8度
4、片廻山、682m、16.3km、14度
5、海見山、869.8m、18.2km、14.5度
6、野登呂山、452.7m、4.8km、20.2度
7、堂床山、859.5m、14.8km、22.2度
8、小掛山、815.9m、18.8km、26.1度
9、福王寺山、495.9m、11km、26.8度
10、螺山、474.6m、8.5km、29度
11、備前坊山、789.2m、17km、33.8度
12、押上山、321.1m、6.2km、36.2度
13、権現山、396.8m、4.8km、45.3度
14、534m、534m、7.9km、47.1度
15、阿武山、585.9m、6.5km、48.6度
16、押手山、706.4m、15.5km、53.7度
17、675m、675.2m、11.2km、59.3度
18、白木山、888.9m、15km、60.1度
19、776m、776m、13.2km、61.5度
20、758m、758m、12km、62.2度
21、ガガラ山、212m、2.3km、63.1度
22、中尾山、798m、12.6km、63.2度
23、鬼ヶ城山、736.9m、12.3km、66.9度
24、安駄山、734.8m、19.2km、72.1度
25、高鉢山、705.4m、15.8km、77.4度
26、椎村山、282m、12.8km、79.2度
27、武田山、410.5m、1.3km、80.9度
28、中山、283.5m、13.3km、81.6度
29、木ノ宗山、412.6m、10.4km、84.5度
30、長者山、571m、14.1km、92.9度
31、三本木山、485.9m、11.9km、95度
32、二ヶ城山、482.7m、8km、95.5度
33、曽場ヶ城山、606.7m、22.2km、95.7度
34、鷹の条山、437.7m、10.6km、97.7度
35、藤ヶ丸山、664.9m、11.9km、104度
36、呉娑々宇山、681.7m、11km、108.2度
37、松笠山、374.3m、6.9km、109.3度
38、鉾取山、711.1m、16.6km、114.5度
39、高尾山、424.2m、9.3km、114.7度
40、原山、671.8m、16.8km、119.1度
41、小田山、718.8m、22.2km、120.6度
42、洞所山、641m、16km、123度
43、牛田山、260.6m、5.8km、126度
44、茶臼山、271m、11km、126.9度
45、日浦山、345.3m、12.7km、128.4度
46、城山、592.5m、16.9km、130度
47、金ヶ燈篭山、531.5m、16.8km、136.6度
48、二葉山、189m、6.7km、142.4度
49、灰ヶ峰、736.8m、25.1km、144.2度
50、発喜山、476m、17km、146.5度
51、絵下頭、593m、17.8km、146.9度
52、明神山、502m、16.7km、147.4度
53、黄金山、221.4m、10.9km、151.4度
54、休山、497m、28.3km、152.4度
55、小松尾山、379.3m、18.5km、152.7度
56、上山、391.3m、20.8km、154.8度
57、天狗岩、370m、16.8km、155度
58、天応烏帽子岩山、460m、21.2km、155.2度
59、天狗城山、293m、19.2km、156.1度
60、後火山、455.4m、38.1km、168.1度
61、古鷹山、375.7m、22km、169.2度
62、クマン岳、399.4m、20.7km、171.2度
63、陀峰山、438m、33.7km、174.5度
64、安芸小富士、277.8m、14.9km、177.8度
65、宗箇山、356m、3.1km、178.8度
66、下高山、202.8m、16.9km、180.5度
67、大見山、336.5m、57.3km、181.1度
68、宇根山、541.8m、26.4km、183.2度
69、嵩山、618.3m、61.8km、194度
70、嘉納山、691m、62.3km、196.2度
71、丸山、457.4m、2.1km、203.5度
72、大茶臼山、413m、3.8km、207度
73、弥山、529.6m、22km、208.5度
74、鈴ヶ峰東峰、312m、8.9km、209.5度
75、岩船岳、466.3m、26km、210.7度
76、鈴ヶ峰、320.1m、9km、213.3度
77、経小屋山、596.1m、25.4km、223.4度
78、船倉山、545.5m、19.5km、227.7度
79、極楽寺山、693m、12.9km、236.1度
80、羅漢山、1108.8m、35.4km、252.1度
81、大峰山、1039.5m、20.4km、257.9度
82、窓ヶ山、710.7m、9km、259.8度
83、東郷山、977.1m、11.8km、281.8度
84、十方山、1318.8m、29.2km、294.1度
85、恐羅漢山、1346.2m、32km、299.4度
86、岳山、521.1m、6km、312.5度
87、深入山、1152.5m、30km、316.2度
88、刈尾山、1223.2m、34km、320.3度
89、尻高山、556.2m、8.2km、330.4度
90、荒谷山、630.9m、4.5km、347.6度
91、阿佐山、1218.2m、37.1km、352.5度
92、牛頭山、672.3m、12.7km、357.9度
そのほか
高野賢彦『安芸・若狭 武田一族』新人物往来社 (2006/10)
参考山行記
広島湾岸トレイル(HWT)・モデルコース
- Akimasa Net(2016年01月16日)山行記(このページ)
武田山~火山~丸山~大茶臼山
(出発:JR大町駅(可部線)、帰着:己斐峠(JR西広島駅―山陽本線))